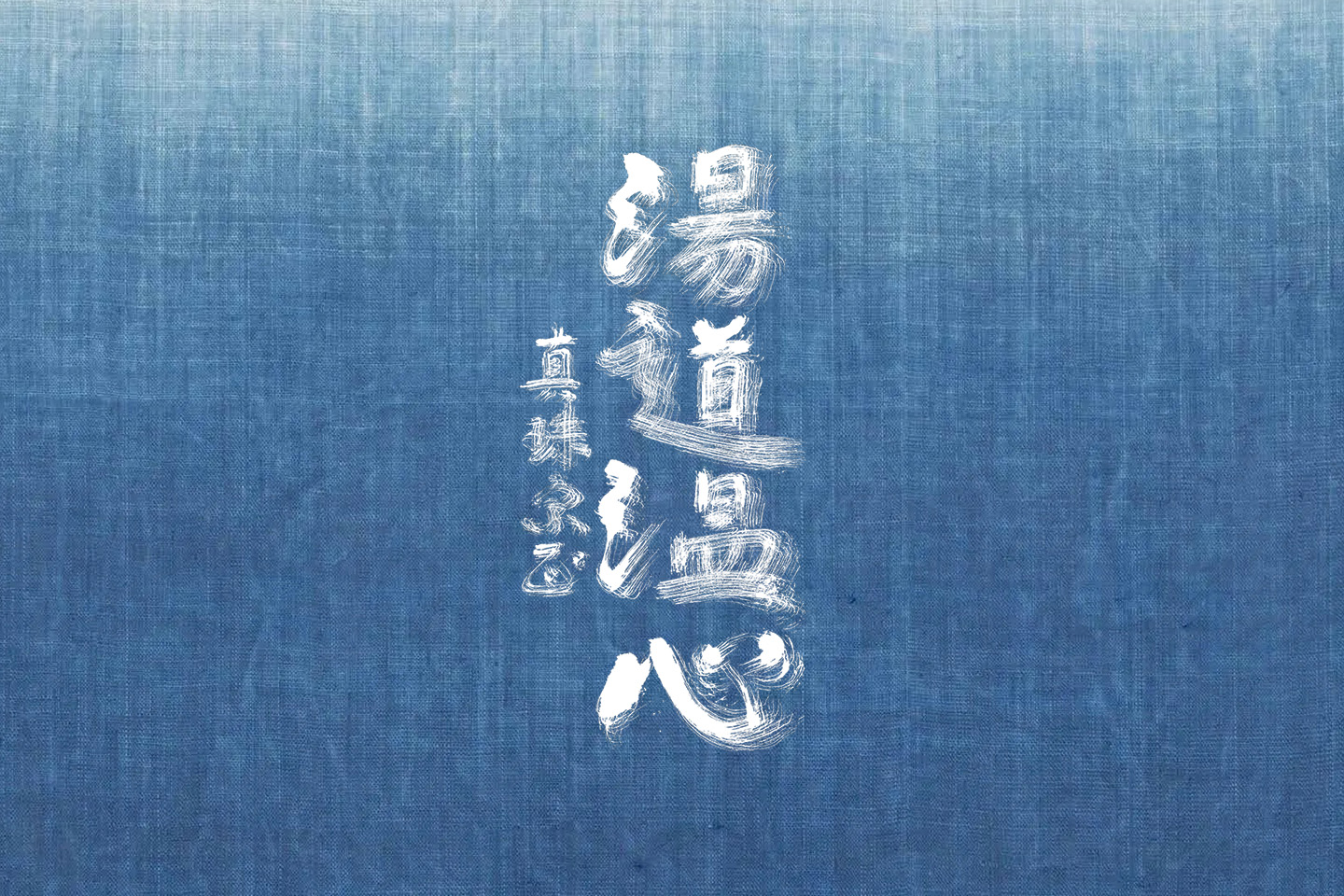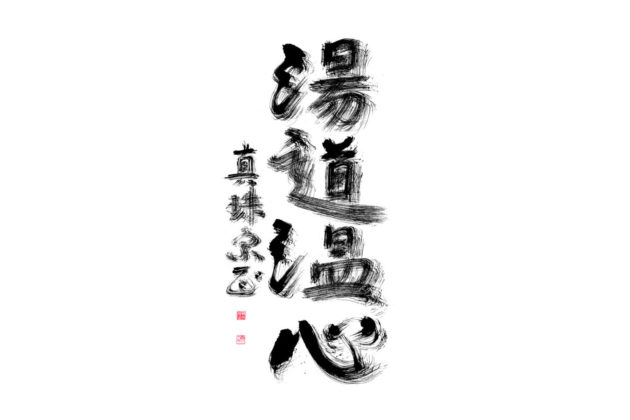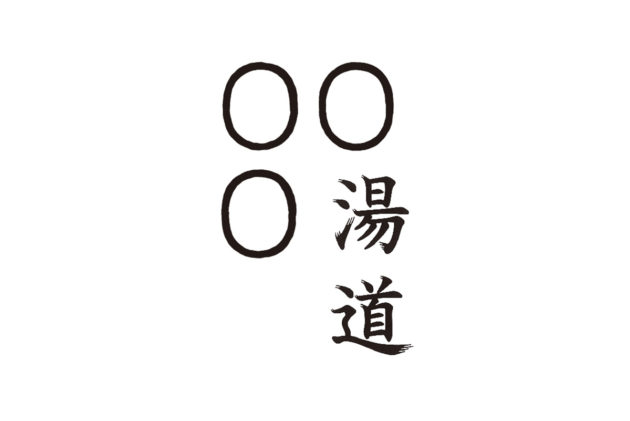-
#カルチャー
#日本文化
新しい「湯の道」
を切り拓く
日本には代々受け継がれてきた「道」があります。
お茶を飲むことが文化となり茶道となったように、
日本人が好む「入浴文化」もいつか
「道」になるのではないか。
そう考えたお風呂愛好家の小山薫堂が、
入浴文化を道とすべく、
「湯道」を拓きました。
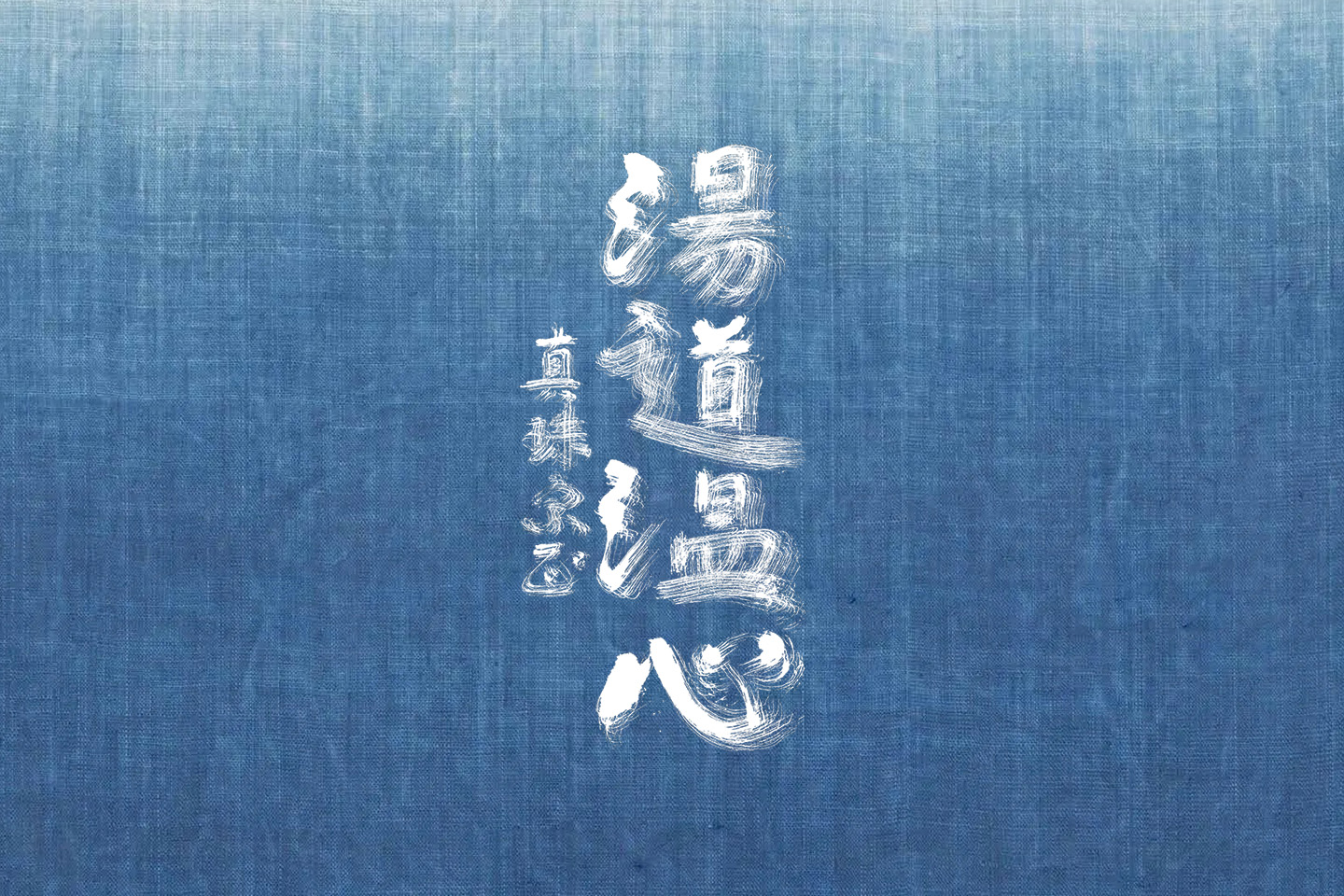
プロローグ
湯道は作法にあらず。
湯に向かう姿勢なり。
「茶道」や「華道」は日本の人々が数百年かけてつくり上げてきた芸術の一形態です。そして今ここに、新たな「道」が生み出されようとしています。
「湯道」──小山薫堂が提唱するのは、「入浴」の精神と様式を突き詰めることで完成する新たな「道」。
「茶を飲むという日常行為を文化芸術まで昇華させた茶道の素晴らしさに改めて感動したとき、自分の大好きな入浴という行為もまた日本独自の文化であることに気づき、いま湯道という活動を始めれば、いつかは本当に『道』として定着するのではないかと思いました」
「入浴」が
ひとつの様式美
となりうる可能性へ
湯道の三つの精神
一、 感謝の念を抱く
湯に浸かるたびに、この日常が特別であることを改めて想い、この環境に感謝すべし。
二、 慮る心を培う
湯に浸かる者、常に次客もしくは隣客の気分となり、慮る心を培うなり。
三、 自己を磨く
湯の力を借りて頭を空にし、ありのままの自己と対峠することで心を癒すべし。
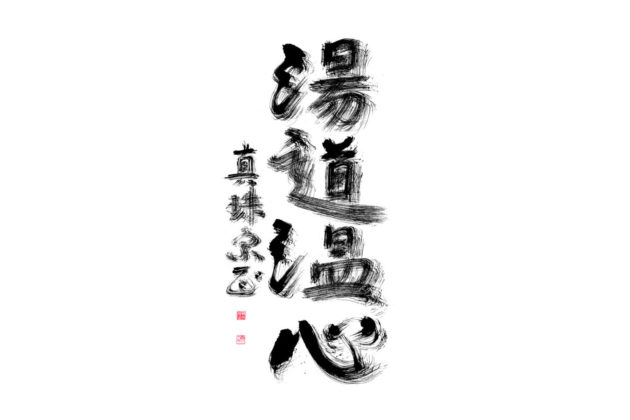
現代に生きる日本人が日常の習慣として疑わない「入浴」という行為。しかし冷静に考えるならば、飲料水を沸かして湯にし、そこに人が入るという贅沢な行為が習慣化されている国は、この地球上に数えるほどしか存在しません。
とするならば、日本の入浴は、現代に存在する類稀なる生活文化であり、その精神と捺式を突き詰めてゆくことで 一つの「道」になると確信しました。
湯道では、「感謝の念を抱く」「慮る心を培う」「自己を磨く」の精神に寄り添いながら、日本の伝統工芸を「道具」として使用することで、職人たちの技や伝統を保護継承します。
また、湯に浸かる喜びを世界中の人々と分かち合うことで、日本の文化や魅力を大いに発信できると信じています。
湯道は今、はじまったばかり。
正解とする形は、一人ひとりの中にあります。
湯を愛する私たちの心が時間によって磨かれ、穢れた想いが洗い流された時、本当の湯道が完成するのです。
湯道提唱者 小山薫堂
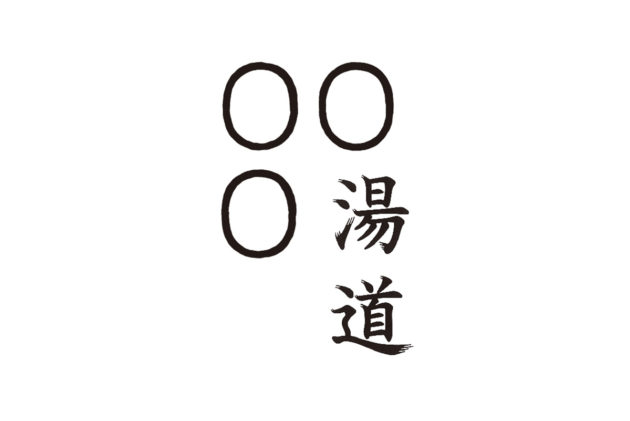
平成27(2015)年6月「湯道」開道
令和2(2020)年10月「一般社団法人湯道文化振興会」設立
湯に浸かる喜びを世界中の人々と分かち合い、日本の職人たちの技や伝統の保護継承へ貢献しながら日本の文化や魅力を発信していきます。